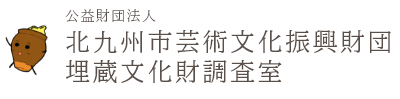穴生諏訪遺跡第2地点
所在地 :北九州市八幡西区穴生二丁目
調査時期:令和7年5月15日~6月30日
調査面積:660㎡
調査の内容
本遺跡は洞海湾の最深部にあり、割子川の東岸に位置している。河川の氾濫原にあるが、近世の耕作土と近代の造成によって2mほど嵩上げされており、現在の標高は約5mである。
近世の耕作土の下には遺物包含層が堆積しており、古墳時代の土師器が多く出土している。また、中世の瓦質土器や青磁碗、古代の須恵器の埦や坏と思われる破片なども確認されている。この遺物包含層の上面では遺構を検出した。西端部で確認された溝状遺構は近世の遺物を含んでおり、当該期の遺構だと考えられる。埋没の過程で溝状遺構が縮小されると同時に、西側には上面が平坦な土塁状の高まりが形成されており、溝状遺構に沿って道が整備されたものと考えられる。明治32年測図の地図には、調査区付近に水田の脇を抜ける道が描かれており、これに相当するものであろう。
また、遺物包含層の下位では、黄灰〜緑灰色を呈する基盤層が見られ、この面にて自然流路を検出した。自然流路は上層に灰色砂質土、下層に砂礫層が堆積し、砂礫層は部分的に腐植土や青灰色粘土層を含んでいる。上・下層ともに遺物が多く出土しており、特に砂礫層には完形品の土師器が多く含んでいる。なお、遺物包含層3層で確認された土器溜りはこの自然流路の岸部分に位置しており、意図的に置かれていたものの可能性がある。
これらの状況から確認された自然流路は集落に近接していたことが想定され、周辺の古墳時代の集落を考える上で貴重な資料を得る事ができた。

遺跡遠景(南から)

調査区全景(南東から)

自然流路岸部遺物出土状況(北から)
主な遺構
| 古墳時代・古代〜中世・近世 |
自然流路、土坑、溝状遺構、ピットなど |
主な遺物
| 古墳時代・古代〜中世・近世 |
古墳時代の土師器、木製品、古代の須恵器、 中世の瓦質土器、青磁、近世の陶磁器、瓦など |
| コンテナ | 69箱 |