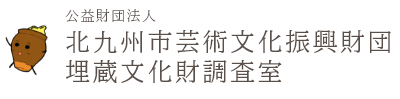菅原神社遺跡10区
所在地 :北九州市八幡西区堀川町2
調査時期:令和6年3月27日~7月5日
調査面積:2,300㎡
調査の内容
本遺跡は八幡西区堀川町2に所在し、調査区はJR筑豊本線の旧線路用地内に位置する。調査区の東側では堀川が北流しており、西側では調査区と現道の間が崖となっている。調査区内では、北端部と南西端部において岩盤が露出しており、この部分は西側から延びる丘陵の尖端部に位置している。これより下位は低地で、ここに遺物包含層が堆積する。遺物包含層は大きく4層に分かれており、最上層の黄褐色土、上層の灰褐色〜灰色粘土、下層の黒色腐植土、最下層の砂層が確認されている。全ての層から6〜7世紀の須恵器が多く出土しているが、最上層は近世、上層には中世の遺物をわずかに含んでおり、それぞれ当該時期の堆積の可能性がある。また、弥生時代中期と思われる土器片も出土している。遺物包含層は低地全体に堆積しているが、南部よりも北部にて多くの遺物が出土しており、場所により遺物量に粗密がある。
なお、砂層や腐植土が堆積している状況から、堀川以前にあった河川もしくは湿地であったことが想定される。
北側岩盤部から下る斜面にはミカン割り材を利用した矢板杭が並び、水場に接した何らかの作業場があったことが想定される。
また、最上層の黄褐色土層の上面では、コンクリート構造物とレンガ敷き遺構が確認されており、これらは明治期の構造物だと考えられ、周辺からは当時の九州鉄道の標章が描かれた小杯や制服に使われていたと考えられるボタン、「折尾驛」の墨書が残る木札などが確認されている。
遠景(北から)
遺物包含層(土器溜り2)須恵器出土状況(南東から)
矢板杭列(西列)検出状況(北西から)
主な遺構
| 弥生〜古墳時代・中世〜近代 |
矢板杭列、土坑、ピット、レンガ敷き遺構など |
主な遺物
| 弥生〜古墳時代・中世〜近代 | 弥生土器、6〜7世紀の須恵器、土師器、近世〜近代の陶磁器、瓦、レンガなど |
| コンテナ | 285箱 |